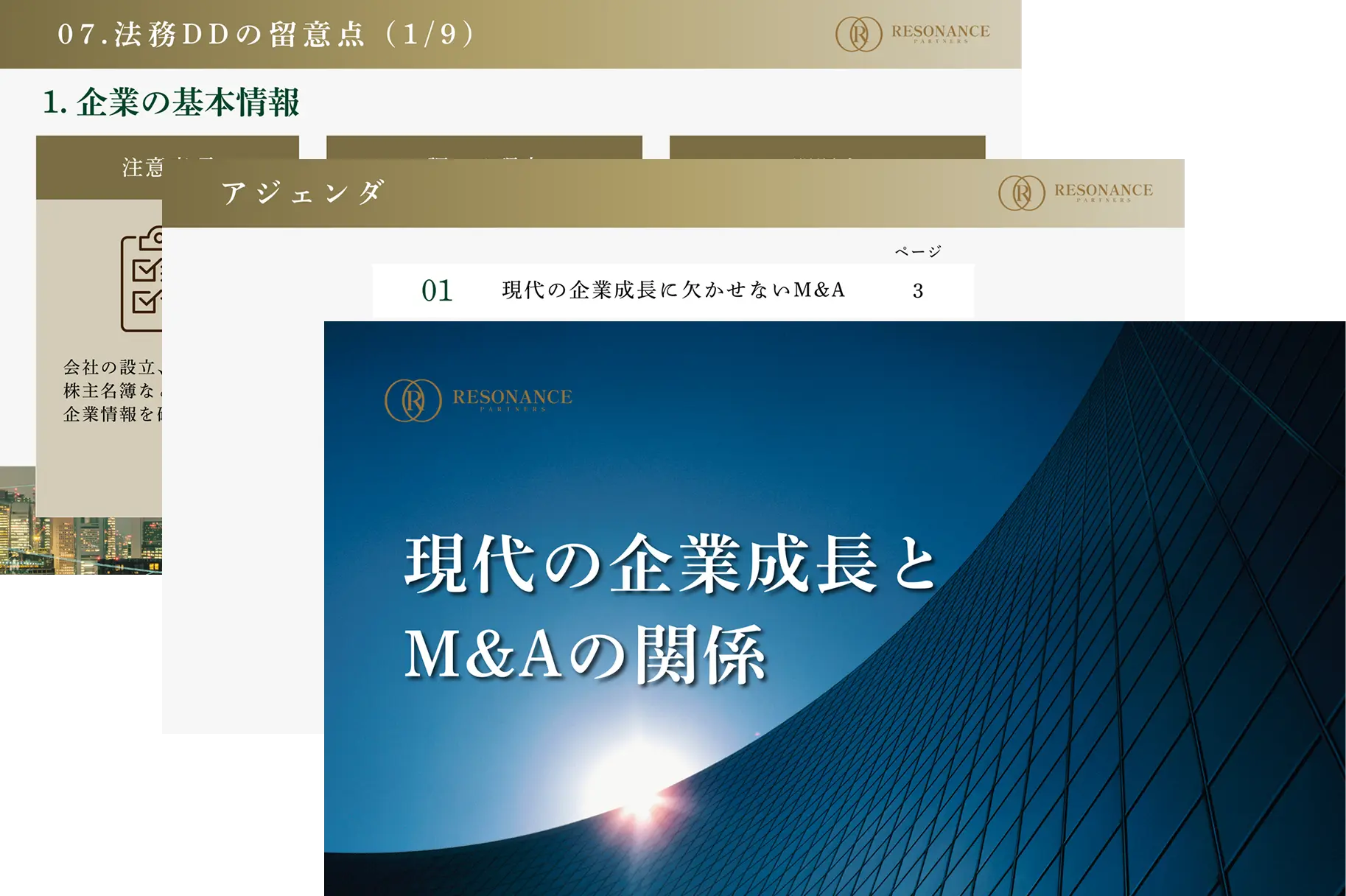【専門家解説】よくある質問と回答で学ぶデューデリジェンスの基礎知識

M&Aを成功させるためには、デューデリジェンスというプロセスが欠かせません。これは単なる形式的な手続きではなく、買収対象となる企業や事業の真の価値を見極め、潜在的なリスクを事前に把握するための重要な戦略的ステップです。デューデリジェンスを適切に行うことで、予期せぬ問題に直面するリスクを低減し、M&A取引の成功確率を高められます。
この記事では、デューデリジェンスがどのようなもので、なぜM&Aにおいてそれほど重要なのか、その基本的な定義と目的から解説します。さらに、実際の調査がどのように進められ、どのような専門家の協力が必要になるのかを具体的にご紹介します。
デューデリジェンスとは何か?その基本的な意味と目的

M&Aを検討する際、相手企業のことを深く知ることは不可欠です。しかし、表面的な情報だけでは見えないリスクや、将来の成長性に関わる重要な要素が隠されていることがあります。そうした情報を明らかにし、M&Aの成否を左右する重要なプロセスがデューデリジェンスです。
ここからは、M&Aにおけるデューデリジェンスが具体的に何を指し、なぜ実施する必要があるのか、その基本的な意味と目的について詳しく見ていきましょう。
デューデリジェンスの意味と定義
デューデリジェンス(Due Diligence)という言葉は、「当然払うべき注意」を意味し、M&Aにおいては、買い手側が買収対象となる企業や事業を深く調査し、その価値やリスクを精査する一連の活動を指します。この調査は、通常、基本合意契約の締結後、最終契約の締結前というM&Aプロセスの非常に重要な段階で実施されるのです。
具体的には、対象企業の
- 財務状況
- 法的な問題
- 事業の将来性
- 組織体制
- ITシステム
など、多岐にわたる側面から徹底的な情報収集と分析を行います。この調査を通じて得られた情報は、単に相手企業の実態を把握するだけでなく、M&A取引における買収価格の適切性や、最終的な契約条件を決定するための重要な根拠となります。
デューデリジェンスは、M&Aにおける「情報格差」を埋める役割を果たし、買い手が十分な情報に基づいた上で意思決定を行うための、いわば「企業監査」のような位置づけにあると言えるでしょう。
デューデリジェンスの目的
デューデリジェンスを実施する目的は多岐にわたりますが、主に以下の3つの観点からその重要性を理解できます。
デューデリジェンスの進め方と専門家の役割

デューデリジェンスがM&Aにおいて不可欠なプロセスであることは理解できたものの、実際にどのように進められるのか、疑問に感じるかもしれません。ここからは、デューデリジェンスの計画から実行、そして最終的な報告書作成に至るまで、どのような段階を踏んで行われるのかを具体的に解説します。また、なぜ外部の専門家との連携が重要になるのか、そしてその過程でどのような情報管理や配慮が必要となるのかについても詳しく説明します。
調査の流れと期間
デューデリジェンスは、M&Aのプロセスにおいて基本合意契約の締結後、最終契約の締結前に行われる重要な調査フェーズです。
その標準的な流れは、まず買い手側がM&Aの目的や対象企業の特性に基づき、どの分野をどこまで深く調査するかという「計画・スコープ策定」から始まります。この段階で、例えば財務、法務、ビジネス、IT、人事といった調査領域が決定されるのです。
デューデリジェンスの標準フロー
計画・スコープ策定
調査範囲と深度を決定
専門家チーム組成
弁護士・会計士・税理士など
資料請求・VDR開設
必要データを安全に共有
分析とQ&A
資料検証・質問応答
面談・現地調査
書類で把握できない実態を確認
報告書作成
調査結果を整理し最終判断へ
期間目安:1〜2ヶ月(規模やスキームにより変動)
スコープが決まると、次に各分野の専門家を選定し「専門家チームの組成」を行います。弁護士、公認会計士、税理士、M&Aアドバイザーなどが役割分担をして調査を進めます。その後行われるのが、売り手企業から必要な書類やデータを開示してもらうための「資料請求とデータルームの開設」です。データルームとは、機密情報を安全に共有するためのオンラインプラットフォームを指します。
専門家チームは、提供された資料を詳細に分析し、不明点や追加で確認が必要な事項について売り手側へ質問を投げかけ「資料の分析とQ&A」を繰り返すのです。必要に応じて売り手企業の経営陣や主要担当者への「マネジメント・インタビューや現地調査」も実施し、書類だけでは把握できない情報を収集します。そして最終的に、これらの調査結果をまとめた「調査報告書の作成」が行われ、買い手側はこれに基づいて最終的なM&Aの判断を下すのです。一般的なデューデリジェンスの調査期間は1〜2ヶ月程度ですが、対象企業の規模や事業の複雑さ、M&Aのスキームなどによって期間は大きく変動する場合があります。
専門家の協力が必要な理由
デューデリジェンスを自社のみで完結させることは、現実的には非常に困難であり、外部の専門家の協力が欠かせません。その主な理由は、M&Aが多岐にわたる専門知識を要求する分野だからです。例えば、財務デューデリジェンスでは、過去の財務諸表の分析から、簿外債務の有無、適切な収益認識が行われているかといった会計・税務に関する高度な知識が求められます。ここで公認会計士や税理士がその専門性を発揮して評価するのは、買い手企業の財務リスクです。
また、法務デューデリジェンスでは、対象企業が抱える契約上のリスク、訴訟の有無、許認可の状況、労務問題などを精査する必要があります。これには弁護士の専門的な法律知識が不可欠です。さらに、対象企業のビジネスモデルや市場環境、競争優位性などを評価するビジネスデューデリジェンスには、M&Aアドバイザーや戦略コンサルタントといった事業分析の専門家が関与します。
これらの専門家は、各分野における深い知見と豊富な経験を持っているため、買い手企業単独では見落としがちな潜在的なリスクや問題点を発見可能です。また、客観的な視点から評価を行うことで、買い手企業がより正確な情報を基にM&Aの意思決定を行えるようサポートします。専門家の活用は、見えないリスクを顕在化させ、M&Aの成功確率を高める上で極めて重要な意味を持つのです。
情報管理と売り手企業への配慮
デューデリジェンスを円滑に進めるための要点
「徹底した情報管理」「売り手企業への配慮」「信頼関係の構築」を核に、交渉・契約・PMIの成功確率を高める。
NDA遵守/アクセス権限の厳格運用/VDR活用で漏洩リスクを最小化。
質問集約・一括提示/現地調査の動線配慮/業務阻害の最小化。
敬意ある対話と誠実な姿勢で、協働の土台を形成。
- NDA(秘密保持契約)の厳守
- 資料の持ち出し制限・操作ログ管理
- VDR(仮想データルーム)でアクセス制御
- 関係者最小限の原則(Least Privilege)
- 質問事項は事前整理&一括提示
- 提出フォーマットの明確化・テンプレ付与
- 現地調査は時間帯・動線に配慮
- 連絡窓口の一本化・SLA運用
- 敬意あるコミュニケーションの徹底
- 意図・背景の共有による納得形成
- 相互依存の可視化で協働促進
デューデリジェンスを円滑に進めるためには、徹底した情報管理と売り手企業への細やかな配慮が欠かせません。M&Aの交渉が水面下で進んでいるという事実が外部に漏洩することは、売り手企業にとって従業員の動揺、主要取引先との関係悪化、ひいては事業価値の毀損に繋がりかねない重大なリスクです。そのため、買い手側はデューデリジェンスの開始前に締結した秘密保持契約(NDA)を厳守し、入手した情報は厳重に管理する必要があります。資料の持ち出し制限やアクセス権限の管理を徹底し、関係者以外に情報が伝わらないよう細心の注意を払うことが求められます。
また、デューデリジェンスは売り手企業の日常業務に少なからず負担をかけるものです。大量の資料提供や専門家からの質問対応、マネジメント・インタビューなど、担当者にとっては通常業務と並行して多くの労力を要します。買い手側は、このような売り手側の状況を理解し、できる限り効率的かつ円滑な情報提供を促す配慮が重要です。例えば、質問事項を事前に整理して一度に提示する、現地調査の際には業務の妨げにならないよう配慮するなど、売り手企業の負担を最小限に抑える努力が必要です。
敬意を持ったコミュニケーションを心がけ、誠実な姿勢で臨むことは、売り手企業との信頼関係構築にも繋がります。これは、デューデリジェンス後の価格交渉や最終契約の締結、さらにはM&A成立後のPMI(経営統合)をスムーズに進める上でも不可欠な要素です。適切な情報管理と売り手企業への配慮は、単なるマナーに留まらず、M&Aの成功確率を左右する戦略的な要素と言えるでしょう。
デューデリジェンスの結果が取引に与える影響

デューデリジェンスは、M&Aにおける企業や事業の調査プロセスですが、その結果は単なる報告書に留まりません。買収の可否や価格交渉、最終契約書の条件など、M&A取引全体に多大な影響を与えます。ここからは、デューデリジェンスを通じて発見されたリスクに対してどのように対応し、その結果を最終的な契約にどう反映させていくのか、具体的な戦略的活用方法について詳しく見ていきましょう。
リスク発見時の対応
デューデリジェンスの過程で、未払残業代や係争中の訴訟、簿外債務といった重大なリスクや問題点が発見されることがあります。このような場合、買い手側はリスクの種類や深刻度に応じて、複数の対応策を検討します。
まず、リスクの金銭的影響が大きい場合、買収価格の引き下げ交渉を行うことが一般的です。たとえば、多額の未払残業代が判明すれば、その支払い義務を考慮した上で買収価格を再評価し、売り手側に減額を求めます。次に、契約書でリスクに対する手当を行う方法があります。最終契約書において、発見されたリスクに関する表明保証条項や補償条項を追加・強化することで、将来的な損害発生時に売り手に責任を負わせるようにします。
また、特定のリスク解消がM&A実行の前提条件となる「クロージングコンディション」を設定するケースもあります。たとえば、重要な許認可の取得ができていない場合、M&A実行までにその取得を義務付けることで、リスクを未然に回避するのです。しかし、発見されたリスクが非常に大きく、事業継続に深刻な影響を与える場合や、改善が困難と判断される場合は、その問題を「ディールブレーカー」(取引を中止せざるを得ないほどの重大な問題)と判断し、交渉から撤退するという選択肢も考慮されることがあります。
表明保証と表明保証保険の活用
デューデリジェンスで全てのリスクを洗い出すことは現実的に困難なため、その限界を補完するリスクヘッジ手段として「表明保証」と「表明保証保険」が活用されます。
「表明保証」とは、M&Aの最終契約において、売り手が買い手に対して、対象会社の財務状況、法務状況、事業内容などに関する特定の事実が契約締結日やクロージング日において真実かつ正確であることを約束する条項です。これにより、もし表明保証された内容が事実に反していた場合、買い手は売り手に対して損害賠償を請求できるようになります。例えば、「財務諸表は適正に作成されている」という表明保証があれば、後から簿外債務が発覚した際に買い手は売り手に対して賠償を求めることが可能です。
さらに、近年「表明保証保険」が注目されています。これは、売り手の表明保証が虚偽であったり不正確であったりした場合に、買い手が被る損害を補償する保険商品です。この保険を活用することで、買い手はM&Aに伴う潜在的なリスクを転嫁し、より安心して取引を進められます。一方、売り手にとっても、表明保証違反による将来の損害賠償リスクを低減できるため、M&A交渉を円滑に進める上で有効な手段となります。表明保証と表明保証保険は、M&Aにおけるリスク管理の重要な要素であり、双方の当事者にとってメリットのある仕組みです。
成功するM&Aのためのポイント
M&Aを成功させるためには、デューデリジェンスを単なる手続きとしてではなく、戦略的なプロセスとして捉えることが重要となります。
まず、案件の特性に応じた適切な調査範囲の設定が不可欠です。限られた時間とコストの中で最大限の効果を得るため、重要性の高い項目に焦点を絞り、優先順位をつけて調査を進める必要があります。また、財務、法務、税務、ビジネスなど多岐にわたる専門分野に対応するため、最適な専門家チームを組成し、緊密に連携することも成功の鍵となるのです。
デューデリジェンスで得られた調査結果は、単にリスクを報告するだけでなく、買収価格の交渉材料や、買収後の経営統合(PMI)計画の策定に戦略的に反映させる必要があります。例えば、発見されたリスクに対しては、価格調整、契約上の手当(表明保証、補償条項など)、またはリスク回避のための具体的な計画を立案するなど、実務的な対応を講じることが求められます。
中小企業におけるデューデリジェンスの特徴と注意点

M&Aにおけるデューデリジェンスは、大企業と中小企業とでその特性や進め方に違いがあります。特に中小企業のM&Aでは、リソースの制約や経営体制の特性といった中小企業ならではの状況を踏まえて、デューデリジェンスを進めなければなりません。ここからは、中小企業のデューデリジェンスがどのような特徴を持ち、どのような点に注意して進めるべきかについて詳しく解説していきます。
中小企業のデューデリジェンスの課題
中小企業のM&Aにおけるデューデリジェンスでは、いくつかの特有の課題に直面することがあります。まず、予算や時間といったリソースが限られているため、大企業のように広範かつ詳細な調査を行うことが難しい場合です。調査範囲を絞り込み、効率的に重要なリスクを特定する能力が求められます。
次に、会計帳簿の整備状況や経理処理が、大企業に比べて不十分なケースです。公私混同の経費計上や、正確な財務情報がタイムリーに作成されていない場合があり、財務デューデリジェンスの精度に影響を与える可能性があります。また、オーナー経営者への依存度が高く、事業の属人性が強い点も課題です。特定の人材に技術や顧客基盤が集中している場合、M&A後にその人材が流出すると事業継続に支障をきたす「キーパーソンリスク」が顕在化する可能性があります。
さらに、多くの中小企業では、財務諸表に対する監査を受けていないため、その信頼性を独自に確認する必要があります。これらの課題は、デューデリジェンスの難易度を高め、潜在的なリスクを見落とす原因となることがあるため、慎重な対応が不可欠です。
M&A仲介会社のサポート活用
中小企業のデューデリジェンスにおける課題を克服するためには、M&A仲介会社やM&Aアドバイザーのサポートを積極的に活用することが非常に有効です。
M&A仲介会社は、提携する公認会計士や弁護士などの専門家ネットワークを持っていることが多く、これらを活用することで、コストを抑えつつ質の高い専門的な調査を実現できます。これにより、限られた予算の中でも、財務、法務、税務といった重要な分野のリスクを適切に評価することが可能です。
M&A仲介会社は、買い手企業の状況に応じてデューデリジェンスの調査範囲を適切に絞り込む提案も行います。中小企業では全ての分野を網羅的に調査することが難しい場合でも、M&A仲介会社が重要度の高い項目を見極め、リスクの高い領域に焦点を当てた効率的な調査計画を立案することで、最小限のリソースで最大限の効果を得ることが可能です。例えば、特に重要な財務・法務に絞り込んだミニマムなデューデリジェンスの提案もできます。
また、売り手企業のオーナーとの円滑なコミュニケーションを仲介する役割も重要です。デューデリジェンスは売り手企業にとって負担となる側面もあるため、M&A仲介会社が中立的な立場で両者の調整役となることで、調査がスムーズに進行し、信頼関係を損なうことなく取引を円滑に進められます。専門家の活用は、中小企業のM&Aにおけるリスク管理と円滑な取引実現に必要な要素と言えるでしょう。
中小企業の企業価値評価のポイント
中小企業の企業価値評価において、デューデリジェンスの結果は最終的な買収価格を決定する上で極めて重要な要素となります。特に中小企業の場合、オーナー経営者の報酬やプライベートな支出が会社経費として計上されているなど、会計帳簿上の利益と実態の収益力に乖離があることが珍しくありません。
そのため、デューデリジェンスで財務状況を詳細に分析し、これらの費用を調整して「正常収益力」を算出することが、適正な企業価値を評価する上で不可欠です。この正常収益力は、将来のキャッシュフローを予測する際の基礎となり、評価額の根拠となります。
さらに、デューデリジェンスで明らかになった事業上のリスクも、企業価値評価に大きく影響します。例えば、特定の取引先への売上依存度が高い場合や、キーパーソンであるオーナーの退任によって事業継続が困難になるリスクなどです。これらのリスクは、将来のキャッシュフローの不確実性を高めたり、事業リスクとして割引率に反映されたりすることで、最終的な企業価値評価額の修正に繋がります。
デューデリジェンスを通じて、潜在的なリスクや事業の実態を正確に把握し、それらを企業価値評価に適切に反映させることで、買い手企業は過大な買収価格を提示するリスクを回避し、より合理的な意思決定を行うことが可能です。
さらに実務的な観点からデューデリジェンスの手順を整理したい方は、「【ステップバイステップ】新人からベテランまで使える!デューデリジェンスプロセスの標準化ガイド」もご参照ください。調査チームの組成や情報管理の要点、成功のための工夫を段階的に学べる内容で、本記事の基礎知識とあわせて活用いただけます。
まとめ:デューデリジェンスの重要性

これまで見てきたように、デューデリジェンスはM&Aのプロセスにおいて、単なる形式的な調査ではありません。それは、譲り受け側がM&Aという重大な経営判断を下す上で、対象企業の持つリスクを正確に把握し、企業価値を適正に評価するための不可欠な戦略的プロセスです。潜在的なリスクを洗い出し、M&A後の統合プロセスを円滑に進めるための情報を得ることは、取引の成功確率を飛躍的に高めます。
デューデリジェンスの知見を価格交渉や契約条件の調整に戦略的に反映させ、表明保証や表明保証保険といった手段も適切に活用することで、予期せぬトラブルを回避し、投資の価値を最大限に引き出せます。大企業から中小企業に至るまで、M&Aの規模や複雑性に関わらず、デューデリジェンスはその本質的な重要性を失うことはありません。この理解を深め、今後のM&A実務に活かしていただければ幸いです。