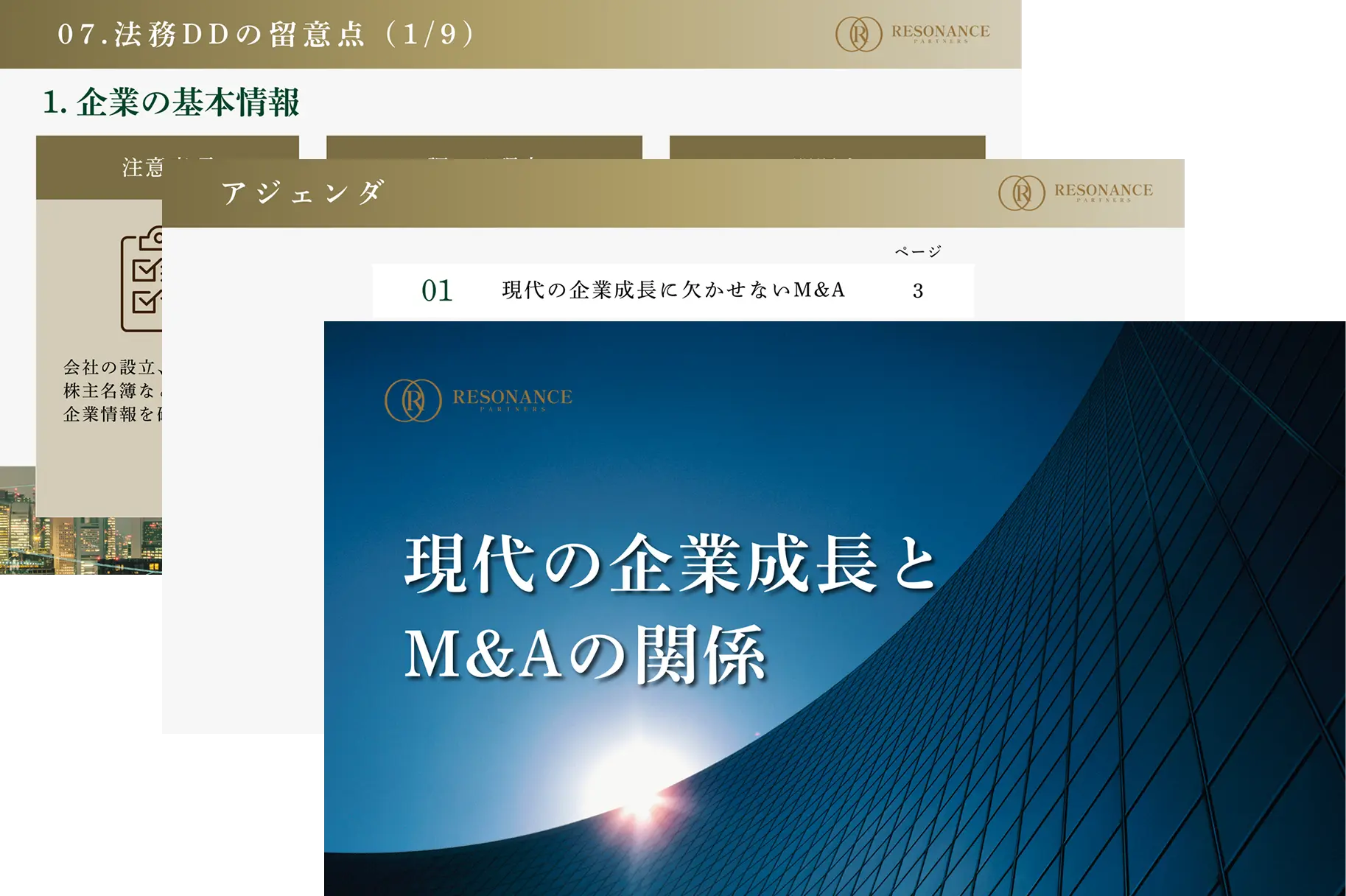初めてのM&A担当者必見!デューデリジェンス費用の適正範囲と削減テクニック
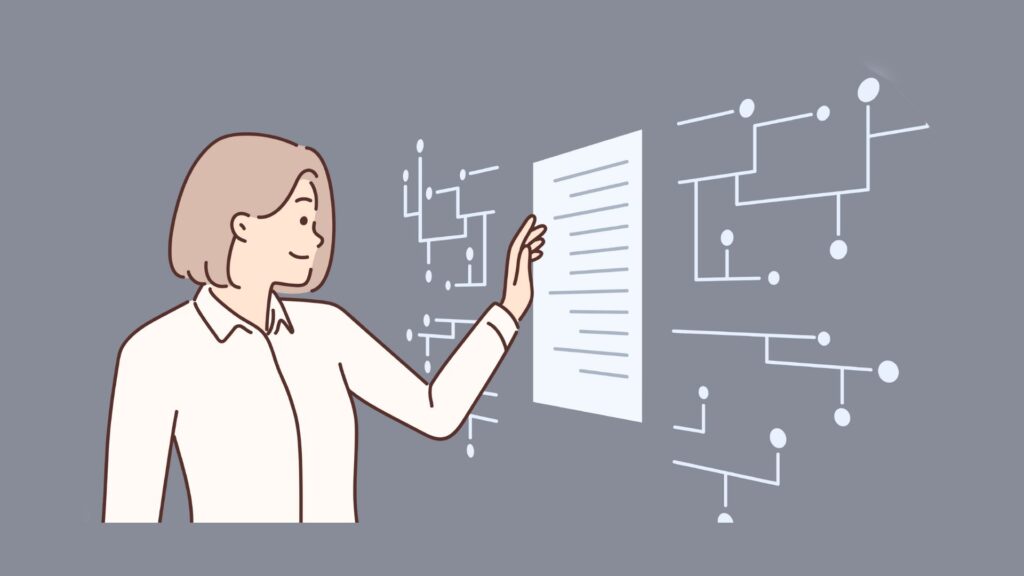
M&A(企業の合併・買収)を検討する際、特に初めて担当される方にとって、デューデリジェンス(DD)は非常に重要なプロセスでありながら、その費用の適正範囲や具体的な削減方法について疑問や不安を抱えることも少なくありません。デューデリジェンスは、買収対象企業の真の姿を深く理解し、潜在的なリスクを洗い出すことで、M&Aの成功確率を大きく左右します。
この記事では、デューデリジェンスがどのような調査であり、なぜ必要なのかといった基本から、その費用がどの程度の範囲で発生するのか、そして最も効率的にコストを抑えながらも調査の質を保つための具体的なテクニックまでを詳しく解説していきます。
デューデリジェンスとは何か?
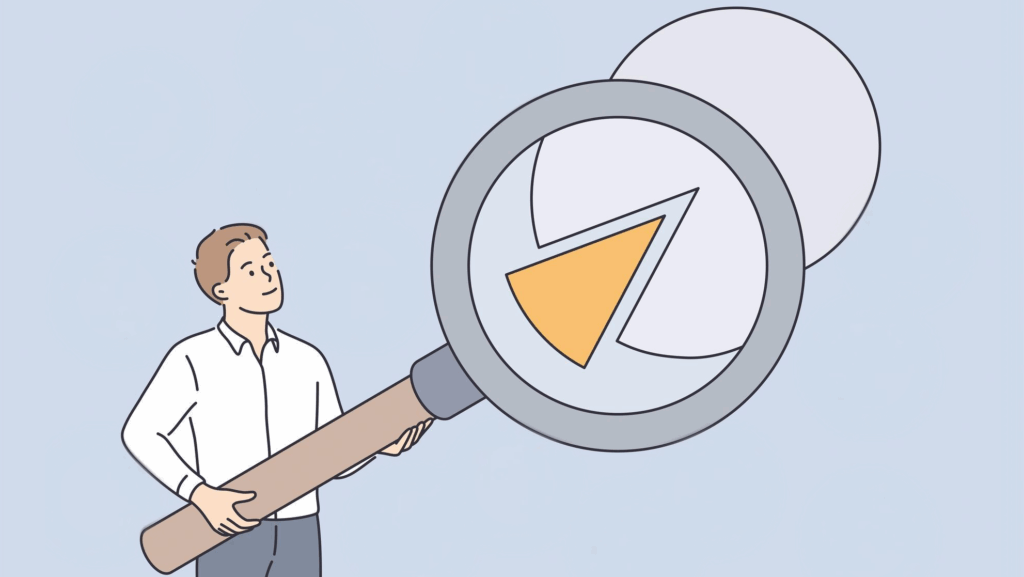
デューデリジェンスとは、M&Aを行う際に、買収対象となる企業の事業内容、財務状況、法務リスク、組織体制などを詳細に調査し、その企業価値や潜在的なリスクを深く理解するためのプロセスです。これは、単に企業の表面的な情報を見るだけでなく、企業内部の隠れた問題点や将来的な成長可能性を徹底的に洗い出すことを目的としています。
デューデリジェンスが必要とされる主な目的はいくつかあります。
簿外債務・未払い残業代・係争等の潜在リスクを特定・評価し、意思決定の精度を高める。
組織文化・人事制度・ITシステム等の実態把握により、具体的かつ現実的な統合計画を設計。
期待シナジーの実現性と、提示価格が本源的価値に見合うかを客観的に検証。
第一に、買収後に発生しうるリスクを事前に把握することです。例えば、簿外債務や未払いの残業代、係争中の訴訟といった隠れたリスクは、買収後に多大なコストや問題を引き起こす可能性があります。これらのリスクを事前に特定し、評価することで、買収の意思決定をより慎重に行えます。
第二に、M&A後のPMI(Post Merger Integration:経営統合)をスムーズに進めるための準備として重要です。デューデリジェンスを通じて、対象企業の組織文化、人事制度、ITシステムといった実態を把握することで、統合計画をより具体的に、かつ現実的なものとして策定できるようになります。
さらに、シナジー効果の分析や、提示された企業価値評価の妥当性を検証する上でもデューデリジェンスは欠かせません。買収によってどのような相乗効果が期待できるのか、そして買収価格が対象企業の本来の価値に見合っているのかを客観的に判断するための重要な情報を提供します。この調査は、財務、税務、法務、ビジネス、人事・労務、IT・システムなど多岐にわたる専門分野で実施されます。
デューデリジェンス費用の適正範囲とは?
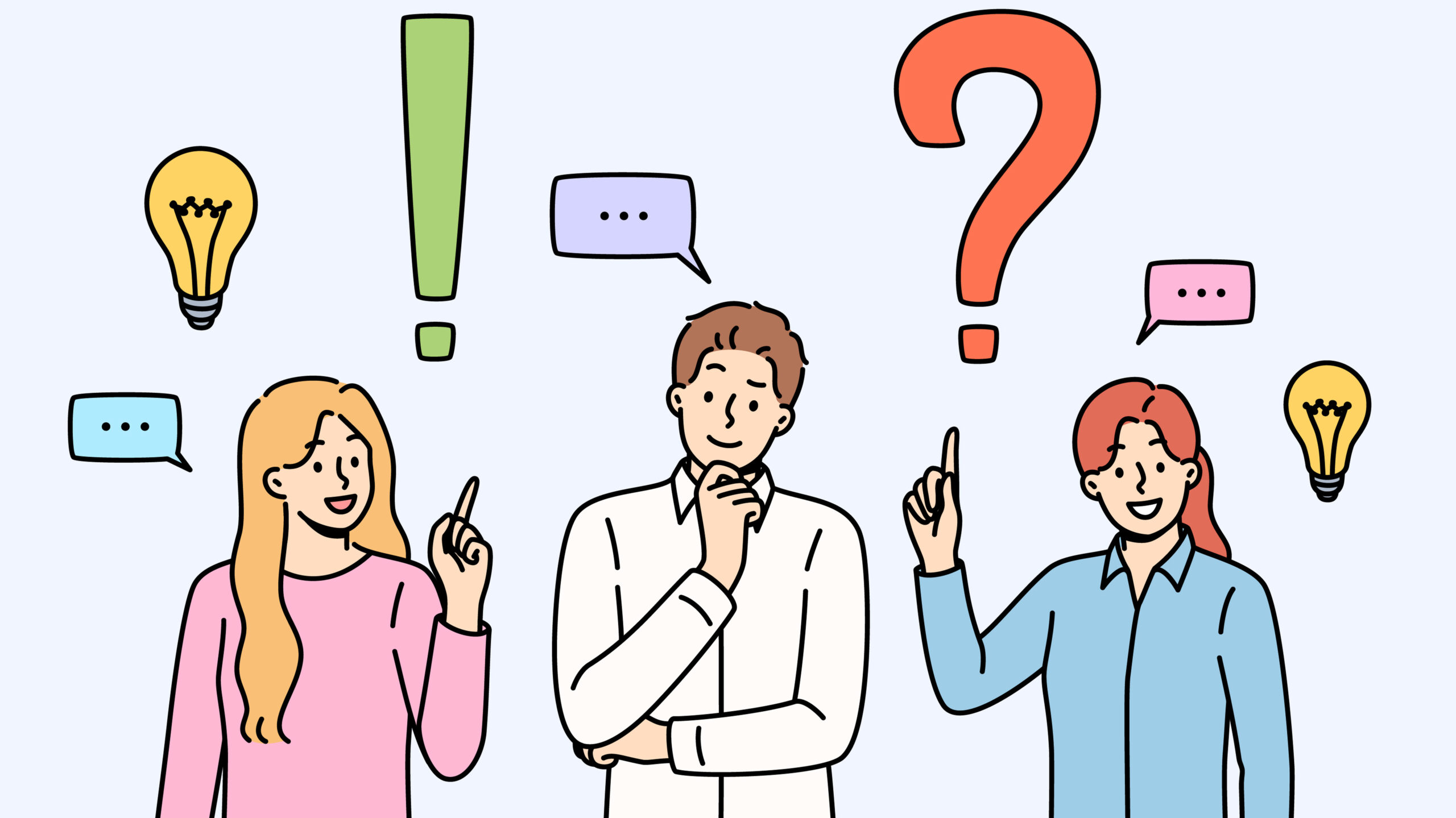
M&Aにおけるデューデリジェンス(DD)の費用は、M&Aの規模、対象企業の業種、事業の複雑さ、そして調査範囲の広さによって大きく変動します。ここでは、デューデリジェンス費用の適正範囲について掘り下げ、具体的な費用の相場感と、その費用がどのような要素で構成されているのかを詳しく見ていきます。
費用相場の概要:企業規模別の目安
デューデリジェンスの費用は、M&Aの対象となる企業の規模によって大きく異なります。一般的に、小規模なM&Aであれば200万円から500万円程度が目安となることが多いです。これは、対象企業が比較的シンプルで、調査範囲も限定的である場合に当てはまります。
中規模のM&Aでは、500万円から1000万円以上、大規模なM&Aや、複数の事業部門を持つ複雑な企業が対象となる場合には、数千万円から1億円を超えることも珍しくありません。これらの金額はあくまで一般的な目安であり、案件の複雑さや予期せぬ問題の有無によって、実際の費用は変動する可能性があることを理解しておくことが重要です。
費用を構成する要素とその内訳
デューデリジェンスの総費用は、主に「外部専門家への委託費用」「自社内の人件費(資料準備など)」「調査期間」といった複数の要素で構成されています。ここでは、これらの費用項目それぞれについて、詳しく掘り下げて解説していきます。
▶︎外部専門家への委託費用
DD費用の主因=外部専門家への委託費
専門家ごとの役割・タイムチャージ・調査範囲/複雑性が費用を左右。
公認会計士・弁護士・税理士・コンサルタントが、それぞれの専門分野で詳細調査を担当。
経験・実績・事務所規模により時間単価が変動。投入時間×人数で費用が積み上がる。
- 時間単価:シニアほど高く、事務所規模でも差
- 稼働時間:調査の深さ・資料量・質問往復で増減
- アサイン:必要スキルに応じたチーム編成
- DDの種類:財務・法務・税務・ビジネス・ITなどの組合せ
- 調査範囲:重要領域への集中か、網羅か(深さ×幅)
- 案件の複雑性:規模、海外要素、係争・会計論点の有無
デューデリジェンス費用の中で最も大きな割合を占めるのが、公認会計士、弁護士、税理士、コンサルタントといった外部専門家への委託費用です。これらの専門家は、それぞれ専門分野に応じたデューデリジェンス(例えば、公認会計士は財務デューデリジェンス、弁護士は法務デューデリジェンス)を担当し、対象企業のあらゆる側面を詳細に調査します。
彼らの報酬は、時間単位で計算される「タイムチャージ」が一般的で、専門家の経験や実績、事務所の規模によって時間単価が異なります。また、依頼するデューデリジェンスの種類や調査範囲の広さ、M&A案件の複雑さによっても、必要な専門家の稼働時間が増減するため、結果的に委託費用に大きな影響を与えるのです。
▶︎資料準備や情報整理のコスト
デューデリジェンスの費用は外部に支払うものだけではありません。見過ごされがちですが、自社内で発生するコストも重要な要素です。これは主に、売り手側から開示される膨大な資料の整理、専門家からの質問事項への回答準備、専門家との会議設定や連携などにかかる自社の人件費(時間コスト)を指します。
これらの社内コストは直接的な費用としては計上されにくいですが、担当者の時間や労力を消費します。そのため、事前に資料の準備を効率的に行ったり、専門家からの質問に迅速かつ的確に回答できる体制を整えたりすることが、専門家の稼働時間を減らし、結果的に外部委託費用を含めた全体のコスト削減に繋がるのです。
▶︎調査期間による費用変動
デューデリジェンスは通常、1ヶ月から2ヶ月程度の短期間で集中的に行われます。この調査期間の長短は、専門家への委託費用に直接的に影響を与えます。期間が長引けば長引くほど、専門家の稼働時間が増え、それに伴い費用も増加するためです。
M&A案件の複雑性や対象企業の情報開示のスピード、予期せぬ問題が発見された場合の追加調査の必要性などによって、当初の予定よりも調査期間が長期化することがあります。そのため、デューデリジェンスの計画段階で、どの程度の期間を想定し、万が一の延長の可能性も視野に入れておくことが、費用をコントロールする上で重要となります。
買い手企業と売り手企業の費用負担の違い
デューデリジェンスの費用を「誰が負担するのか」という疑問は、M&A担当者にとって非常に重要なポイントです。原則として買い手企業が負担するケースが多いですが、売り手企業が負担する「セルサイド・デューデリジェンス」という形態も存在します。ここでは、それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。
▶︎買い手企業が負担する場合の注意点
M&Aにおけるデューデリジェンス費用は、原則として買い手企業が負担することが一般的です。これは、買い手企業が自社の投資判断のために、対象企業の財務状況、法務リスク、事業の実態などを詳細に調査する必要があるためです。リスクを最大限に把握し、M&A後の経営統合をスムーズに進めるための「投資」と考えられます。
経理処理上の注意点は、デューデリジェンス費用は株式購入の意思決定の前後で取り扱いが異なる点です。経理処理上の注意点として、デューデリジェンス費用を含むM&A関連費用は、M&Aが成立した場合と不成立に終わった場合で取り扱いが異なります。
| M&Aが成立した場合 | デューデリジェンス費用やM&A契約書作成のための弁護士費用など、株式取得に直接関連する費用は、原則として取得した株式の取得価額に含めて資産計上される。 |
| M&Aが成立しなかった場合 | 費用は原則として発生した期の損金(費用)として計上される。 |
したがって、デューデリジェンス費用の会計処理については、事前に専門家と十分に協議し、適切に処理を行うことが重要です。これにより、税務上のリスクを回避し、正確な財務状況を把握できます。
▶︎セルサイドデューデリジェンスにおける譲渡企業の費用負担
通常は買い手が負担するデューデリジェンス費用ですが、売り手企業が自ら費用を負担してデューデリジェンスを行う「セルサイド・デューデリジェンス(セルサイドDD)」という選択肢もあります。これは、売り手が自社の企業価値を適切に評価し、潜在的な問題を事前に洗い出して開示することで、M&Aプロセスの透明性を高め、スムーズな進行を目指すものです。
セルサイドデューデリジェンスの目的は、買い手候補に対する情報提供を効率化し、複数の候補先に対して一貫した情報を提供することにあります。これにより、買い手側のデューデリジェンスが簡略化され、時間とコストを節約できるため、結果的に買い手、売り手双方にとってメリットとなる場合があるのです。また、売り手は事前に自社のリスクを把握し、それに対する説明や対応策を準備できるため、買い手との交渉を有利に進めることにも繋がります。
デューデリジェンス費用を削減するテクニック

M&Aにおけるデューデリジェンスは、単にリスクを洗い出すだけでなく、将来的な統合を成功させるための重要なプロセスです。このデューデリジェンスにかかる費用は、M&Aの規模や複雑性によって大きく変動するため、いかに費用対効果を高めるかがM&A担当者の腕の見せ所となります。
本章では、デューデリジェンス費用を単に削減するのではなく、その費用対効果を最大化するための具体的な方法を解説します。
基本合意の早期締結と情報開示の効率化
デューデリジェンス費用を抑えるためには、M&Aプロセスの初期段階での効率化が非常に重要です。特に、基本合意書(LOI: Letter of Intent)の早期締結と、その後の情報開示をいかに効率的に行うかが、デューデリジェンスの期間と総費用に大きく影響します。
▶︎情報開示のタイミングと重要性
デューデリジェンスにおいて、売り手側から買い手側への情報開示がスムーズに行われることは、調査全体の効率性を大きく左右します。基本合意が締結された後、売り手から迅速かつ網羅的に必要書類が開示されることで、買い手側の専門家は無駄な待機時間なく調査を開始できます。これにより、調査期間の短縮が実現し、結果として専門家への報酬、つまりデューデリジェンス費用の削減に直結するのです。
情報開示の遅れや不備は、専門家が調査を進める上で頻繁に質問を投げかけたり、追加資料を要求したりする原因となり、その都度、時間とコストが発生してしまいます。逆に、最初から整理された情報が提供されることで、専門家は効率的に分析を進められ、手戻りも減少します。これは、買い手と売り手の間に信頼関係を構築し、M&Aプロセス全体を円滑に進める上でも欠かせません。
▶︎必要な資料の事前整理方法
買い手側としてデューデリジェンスを効率的に進めるためには、売り手側に対してどのような資料を準備してもらうか、そして自社でどのように情報を整理するかが重要です。具体的には、VDR(バーチャルデータルーム)と呼ばれるオンライン上の安全な情報共有スペースを活用することが非常に有効です。
VDRは、機密性の高いM&A関連書類を効率的に管理・共有できるツールで、情報の散逸を防ぎ、専門家が必要な情報にいつでもアクセスできるようにします。
また、デューデリジェンスを開始する前に、必要な資料のチェックリストを売り手と共有し、事前に準備を依頼しておくことも大切です。例えば、過去数年間の財務諸表、税務申告書、主要な契約書、組織図、人事関連資料など、調査項目に応じた網羅的なリストを作成します。この際、単にリストを渡すだけでなく、資料の形式や種類についても具体的に伝えておくと、売り手側の準備もスムーズに進みます。
このように、事前に資料が整理され、専門家が容易にアクセスできる状態になっていることで、専門家の調査効率は格段に向上します。結果として、専門家の稼働時間を短縮でき、これが直接的にデューデリジェンス費用の削減に繋がるのです。
▶︎仲介会社の活用による効率化
M&A仲介会社やアドバイザーは、デューデリジェンスにおける情報開示の効率化に大きく貢献します。専門知識を持つ仲介会社が買い手と売り手の間に入ることで、コミュニケーションが円滑になり、必要な情報の要求やその整理がスムーズに進むのです。例えば、買い手側からどのような情報が必要か、売り手側からどのような情報が開示可能かといった調整を仲介会社が行うことで、情報の行き違いや不足を未然に防げます。
仲介会社は、M&Aの専門家として過去の経験から「どのような情報が必要か」「どのような形式で提供すれば効率的か」を熟知しています。そのため、売り手に対して効果的な資料準備のアドバイスを提供したり、情報開示のスケジュール管理をしたりすることで、デューデリジェンスのプロセス全体を効率化する役割を担うのです。
これにより、買い手側の専門家が本質的な調査に集中できるようになり、結果として間接的なコスト削減、ひいては全体のデューデリジェンス費用の最適化に繋がります。
調査範囲の適切な設定
デューデリジェンスの費用を削減する上で、調査範囲を適切に設定することは非常に重要です。闇雲にすべての情報を深掘りするのではなく、リスクとコストのバランスを考慮し、本当に必要な部分に資源を集中させる「選択と集中」が不可欠になります。ここでは、その具体的な方法を詳しく解説していきます。
▶︎リスクに応じた調査対象の優先順位付け
対象企業の事業で想定される潜在リスクを把握する。
M&Aの成功に与える影響度が大きい領域に、調査リソースを重点配分する。
影響度が低い領域や、既に十分な情報がある領域は簡易調査または調査範囲から除外する。
費用対効果の高いデューデリジェンスを実施するためには、調査対象の優先順位付けが欠かせません。まず、予備的な情報収集の段階で、対象企業の事業における潜在的なリスクを洗い出すことが重要です。例えば、特定の取引先への依存度が高い、過去に訴訟を抱えていたことがある、あるいは偶発債務が存在する可能性など、事業の継続性や財務状況に大きな影響を与えうるリスクを特定します。
その上で、洗い出されたリスクの中で、M&Aの成功に与える影響度が大きい「ハイリスク領域」に調査リソースを集中させる戦略を取るのです。一方で、影響度が低いと判断される領域や、すでに十分な情報がある領域については、簡易的な調査に留めるか、場合によっては調査範囲から除外するといった判断も必要になります。このように、リスクの大きさに応じて調査の深度を変えることで、限られた予算と時間の中で最も重要な情報を効率的に把握できるでしょう。
▶︎不要な調査を省くための基準
調査範囲を絞り込む際に、「不要な調査」を判断するための明確な基準を持つことが重要です。たとえば、買収金額全体に対して影響が極めて軽微な論点や、企業のビジネスモデル上、過去の実績から見てもリスクが低いと考えられる領域については、詳細な調査を省略する判断も有効となります。これは、すべての事柄を完璧に調査しようとすると、時間と費用が膨大になってしまうためです。
特に、自社のM&Aの目的と照らし合わせ、その買収で「何を知る必要があり、何をそこまで深く知る必要がないのか」を明確にすることが肝心です。例えば、特定の技術獲得が目的であれば、その技術に関する知財や開発体制の調査に重点を置き、それ以外の一般的な労務関係などは簡易な確認に留める、といった判断が考えられます。目的を明確にすることで、効率的かつ費用対効果の高いデューデリジェンスが実現します。
▶︎費用対効果を考慮した調査計画の立案
これまでの議論を踏まえ、デューデリジェンスの費用対効果を最大化するためには、具体的な調査計画の立案が不可欠です。設定した予算内で、先に特定したリスク領域をどの程度の深度まで調査するのかを、詳細な計画書としてまとめることが求められます。この計画書には、各調査項目とその目的、期待される成果物、そして想定される専門家の投入時間や費用を明記します。
作成した調査計画は、デューデリジェンスを依頼する専門家と事前に共有し、内容について合意を得ておくことが極めて重要です。これにより、後から業務範囲が不必要に拡大する「スコープクリープ」を防ぎ、予期せぬ追加費用の発生を抑制できます。また、この計画書は、経営陣に対してデューデリジェンスの目的と費用、そして得られる効果を説明する上での重要な資料となり、透明性の高いM&Aプロセスを推進にもつながるのです。
合意済みの成果物や作業範囲が、期限・予算・要員の再調整なしに少しずつ拡大してしまう現象。 未整理の追加要望や変更管理の不備が主因で、遅延・コスト超過・品質低下を招く。 防ぐには範囲記述を明確化し、変更は影響評価→承認→計画更新の手順を徹底する。
外部専門家の選定と交渉術
デューデリジェンスの費用を削減するために、最も重要な要素の一つが、パートナーとなる外部専門家をいかに選定し、いかに交渉するかです。専門家の能力や経験は、デューデリジェンスの質と費用に直結します。費用対効果を最大化するためには、単に安ければ良いというわけではありません。明確な要件定義に基づいた専門家選びと、効果的な交渉術を身につけることが、コスト最適化の鍵となります。ここでは、その具体的なノウハウを詳しく解説していきます。
▶︎専門家選定時のポイント
デューデリジェンスを依頼する外部専門家を選定する際には、いくつかの重要なポイントがあります。
- M&Aの実績、特に自社と同業界や同規模の案件における経験が豊富であるかを確認することです。経験豊富な専門家は、過去の事例から生じるリスクを適切に評価し、効率的に調査を進められます。
- 財務、法務、税務など、複数の分野のデューデリジェンスを一括で依頼できる「包括的なサポート体制」が整っているかも確認しましょう。複数の専門家と個別に契約するよりも、一つのファームが窓口となって全体を統括してくれる方が、連携がスムーズで、コミュニケーションコストも削減できます。
- 担当者とのコミュニケーションのしやすさも非常に重要です。デューデリジェンスは短期間で集中的に行われるため、密な連携が求められます。不明点や懸念事項をすぐに相談できる関係性を築けるか、専門家が質問に対して迅速かつ分かりやすく回答してくれるかを見極める必要があります。
- 依頼する業務内容に対して、明確で納得のいく見積もりが提示されるかどうかも、選定の重要な判断基準となります。
▶︎費用交渉を成功させるコツ
デューデリジェンスの費用交渉を成功させるためには、いくつかの実践的なコツがあります。
デューデリジェンスの結果を活用する方法

デューデリジェンスを通じて得られた詳細な情報は、M&Aの最終的な条件交渉や、買収後の事業統合(PMI)を成功させるための重要な基盤となります。
例えば、デューデリジェンスで偶発債務や簿外債務、あるいは回収困難な債権など、買収後に発生しうるリスクや問題点が発見された場合、その情報を基に最終的な買収価格の減額交渉を行うことが可能です。これにより、当初の企業価値評価に織り込まれていなかったリスクを価格に反映させ、買い手側のリスクを軽減できます。また、株式譲渡契約(SPA)において、発見されたリスクに対する表明保証条項や補償条項を盛り込むことで、将来的なリスク発生時の責任範囲を明確にし、買い手企業の防御策とすることが可能です。
さらに、デューデリジェンスで把握された対象企業の強みや弱み、組織文化、ITシステムの状態、人材構成などは、M&A後のPMI(Post Merger Integration)計画を策定する上で不可欠な情報です。例えば、ITシステムに統合上の課題が見つかれば、PMI計画にその解決に向けた具体的なステップを組み込めます。また、人事・労務デューデリジェンスで明らかになった組織風土や人材の特性は、統合後の組織再編や人材配置、評価制度の設計に役立ちます。このように、デューデリジェンスの結果を多角的に活用することで、M&Aの成功確度を格段に高められるのです。
デューデリジェンスの進め方を詳しく知りたい方は、
関連記事: 【ステップバイステップ】新人からベテランまで使える!デューデリジェンスプロセスの標準化ガイド
もご参照ください。調査チームの組成や情報管理、成功のための工夫を解説。費用面の理解とあわせて実務での活用が一層深まります!
まとめ:適正なデューデリジェンス費用でM&Aを成功させるために

M&Aにおけるデューデリジェンス費用は、一見すると大きなコストに見えるかもしれません。しかし、これは単なる支出ではなく、将来的なリスクを回避し、M&Aの成功確率を高めるための重要な「投資」であると捉えることが大切です。不十分なデューデリジェンスによって見過ごされたリスクは、M&A後に想定外の損失や追加コストとなり、結果としてM&Aの失敗に繋がりかねません。
本記事で解説した「効率的な情報開示」「適切な調査範囲の設定」「賢い専門家の選定と交渉」といったテクニックを実践することで、デューデリジェンスの費用対効果を最大化することが可能です。情報開示の効率化は専門家の作業時間を短縮し、調査範囲の絞り込みは本当に必要な部分にリソースを集中させます。また、適切な専門家を選び、明確な要件で交渉することは、質の高い成果を適正な費用で得ることに繋がります。適正な費用で質の高いデューデリジェンスを行い、企業の持続的な成長を実現していきましょう。